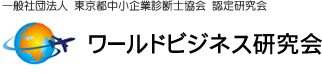駐在員としてオランダに着任した時(1995年)、先輩赴任者が「ティーバッグの捨て方」を教えてくれました。
<使用済みティーバッグの捨て方>
1 紅茶の入っている袋、紙、糸、ホッチキスの針、4つに分解する
2 紅茶の入っている袋は各家の玄関前にある緑色のゴミ箱(グリーンボックス)に入れる
3 紙の部分は紙類のリサイクルボックスに入れる
4 糸の部分は繊維類のリサイクルボックスに入れる
5 ホッチキスは金属類のリサイクルボックスに入れる
つまり、ゴミとして焼却される部分は全くなく、100%リサイクルされるのだよ、と。
もちろんオランダ人がみんな、本当にここまで細かく実践しているかどうかは怪しいところではありますが、ルールに従って捨てるとすれば、これが正しい捨て方だというのです。
実際オランダでのゴミの分別はかなり細かくなっています。
・生ゴミと庭の木の枝・葉っぱ・芝生を刈ったもの(グリーンゴミ)
・紙と段ボール
・ガラス
・缶・プラスチック・紙パック
・揚げ油
・繊維類
・電気製品
・化学物質
・がれき
といった具合です。
ここには、リサイクルできるものはすべてリサイクルして、資源を1gも無駄にしないぞ、という執念が感じられます。

これは「廃棄物」の話ですが、「リサイクル」の前に来る「リユース」も徹底しています。
上記の「ガラス」の分類は主に輸入品であるワインのボトルの捨て方になり、ハイネケンやアムステルといった国産品がほとんどであるビールや牛乳、国産のミネラルウォーターには当てはまりません。なぜなら、ビール瓶などはすべてお店に持っていくと、お店でデポジットの瓶代を返してくれるからです。
各スーパーにはビールのガラス瓶や国産のミネラルウォーターなどのペットボトルを返すベルトコンベアが設置されており、そこに乗せると画像解析で何の瓶かを判断し、入れた本数分xデポジット代金のレシートが印刷されます。1本ずつ入れる必要はなく、プラスチックのビールケースに入れたままベルトコンベアに乗せてもちゃんと読み取ってくれる優れものです。そのレシートを会計時に出すと、買い物の代金からその分を引いてくれるという仕組みです。

また、「リユース」の前に来る「リデュース」に関しても、1995年当時ですでに、スーパーでは袋はもらえず、バッグを持っていくのを忘れると手で持てる分だけ買うか、結構高額な買い物袋を買うかしかありませんでした。
それではなぜ、オランダ人はこんなにもリサイクルに熱心なのでしょうか?
そのヒントはオランダの分別の特徴である「グリーンゴミ」(生ゴミと庭の木の枝・葉っぱ・芝生を刈ったもの)にあります。
「世界は神がつくったが、オランダだけはオランダ人が造った」と言われます。
実際オランダの国土のうちの4分の1は干拓地です。海を堤防で仕切って中の水を風車で汲み出すことによって、オランダ人が作り出した土地なのです。オランダには海を埋め立てるような土を持ってこれるような山は存在しませんから、「埋立地」ではなく、海から海水を汲み出しただけの土地で、標高は海面下であり、海の底ですので砂地で土に養分はなく、そのままでは耕作はできません。ですので、この海の底の砂地で農業を行うために、肥料になるものをすべて注ぎ込む必要があったというのが、オランダ人のリサイクルに賭ける情熱の原点であると言えると思います。
そうして生み出した土地であっても、できる作物は砂地でも育つチューリップやジャガイモに限られます。「割り勘」ことを「ダッチアカウント」と呼ぶなど、よく「オランダ人はケチだ」と言われますが、こういったことも、資源の乏しい中で生きていくために培われた「もったいない精神」から来ているのだと思います。
オランダ人の文化や気質を育んだのは、こういったオランダの持つ特殊な「地理的要因」であると考えられるのです。
中小企業診断士 池田真一郎