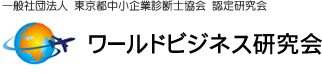欧米という言葉がありますが、実際我々日本人が住むとしたら、日常生活で戸惑うことが多いのはおそらく圧倒的にアメリカでしょう。単一民族ではないにしても、長い歴史の中でコミュニティの基礎を気付いてきたヨーロッパは日常の所作において少なからず我々の感覚に通じるものがあるように思いますが、新しい歴史の中で移民によって急速な発展を遂げてきたアメリカは、言葉にするのは難しいのですが、全く別の社会の雰囲気があります。
筆者が学生の頃からアメリカへ行ったり、逆に日本に来たアメリカ人と接したりする中で、奇異に感じられたことをいくつかお話したいと思います。
●道を聞かれる
二十何年も昔のことになりますが、始めてアメリカを訪れて少々戸惑ったのがこれです。日本では一見して外国人的な人種の人に日本人が道を尋ねるということはほぼ100%ないでしょう。アメリカでは、明らかにアジア系の自分でも、よく道を聞かれます。「こっちが聞きたいくらいだってのに!」と思いながら、「I’m a stranger here, sorry」と返すと、「なんだそうか!」とばかりに何事もなかったように立ち去っていく姿に、移民国家の姿を重ね合わせて感じたものです。
人種で地元民かstrangerかは判断されない。アメリカという国の成り立ちから考えれば至極当然のことのようですが、実際に現場に遭遇すると、やはり戸惑うものです。
●英語を話せない人に冷たい
アメリカ人は英語が下手な外国人に対して、日本人が外国人にするように手取り足取り、紙とペンまで使ってなんとか相手の意思をくみ取ってあげようなんて気づかいは全くないようです。
これも初めてアメリカの土を踏んだ頃の話ですが、受験英語の知識だけで挑んだ現場は、想像以上にシビアだったのを覚えています。世界の盟主の言語、世界の共通語という自負もあるのかもしれませんが、移民国家ゆえに確固たる共通基盤を必要とするアメリカのような国では、英語というツールもその一つなのだと思います。フランス人はフランス語を話さない外国人に冷たいとよく言われますが、アメリカ人はそれ以上だと個人的には思いますね。
ファストフードの店員から「こいつ何を言ってるんだ??」みたいな目で何度もにらまれたのはアメリカデビューの頃の良い思い出です。
ただ、長い米国駐在による知見を持つ当分科会メンバーによると、こういう雰囲気は地域によっても強弱があるそうで、やはり東部などではその傾向が強く、西部の大都市周辺などでは、その傾向もやや異なってくるそうです。
●全く英語を話せないアメリカ人もいる!
アメリカは移民国家ゆえ、英語は全く理解できない人もいるというのは理に適っています。これもまたその頃の話ですが、マイアミのファストフード店で、「ハンバーガー、ワン!」がどうしても通じずに、自分の発音はそこまで酷いのか(笑)と思いきやそうではなく、結局「ハンバーガー、ウノ!」とスペイン語も使って言わなければ、その店員には通じなかったという話です。
この人達がNYのタイムズスクウェアあたりに行った時はどうするのだろうなどとも思いましたが、南部の方ではスペイン語だけで日常が事足りるコミュニティが存在するということだと思いますので、これもまたアメリカなんだなあと感心した次第です。我々には、日本語が全く通じない日本人のコミュニティって、ちょっと想像しづらいですよね。
●IDにうるさい
アメリカでは、いたるところでID確認が徹底しているところもさすが移民の国だなと感じます。人種が違えば見た目も違うわけで、そんな曖昧なものに年齢確認を委ねることはできないわけです。私も、30代になるころまでは、ビールを買うのにいつもパスポートの提示を求められていたような気がします。さすがに最近は言われませんが、笑
●(特に子供の)セキュリティに厳しい
「秋深し となりは何をする人ぞ」と芭蕉は詠みましたが、アメリカ人は四季を通じて芭蕉の境地にあると言えます。これこそ移民国家の真髄かもしれませんが、移民が集まった国においては、自らの属する文化圏の考え方や習慣が、隣人にも通用するとはならないわけで、日本との根本的、決定的な違いと言っても良いと思います。必然、自分と家族の身を守るためのセキュリティには非常に厳しくなります。
アメリカでは子供だけで公園で遊んだり、通学したりなどということは考えられず、そのあたりのやや殺伐とした雰囲気、街の生活感の欠如が、私が初めてアメリカを訪れた頃に感じた違和感の正体なのかもしれません。
逆に、初めて日本を訪れるアメリカ人が一様に目を丸くして驚くのが、日本の子供たちです。中には小学校低学年くらいの子が、背中より大きいランドセルを背負って一人で山手線に乗ったりしていますが、アメリカ人からしてみれば異文化どころか別の惑星に来たんじゃないかと思うくらいの衝撃のようです。
(追記)余談ですが、1~2年ほど前に埼玉県議会が突如上記と同様の対応(例えば、子供を自宅等で一人にしてはいけない。朝、ゴミを出しに行く間だけでも)を保護者に求める子供保護条例のようなものを提出し、県民の大反対を食らってわずか数日で撤回に追い込まれるというドタバタ劇を演じました。音頭を取った自民党の県議は、アメリカの真似で“子育て族”としての名を上げようとしたのかもしれませんが、県(国)民生活の実情、文化の違いを無視したあまりにもお粗末な出来事でしたね。いつか当分科会の記事を読んでもらいたいと思っています。
●酒に厳しい
アメリカではもちろん酒を買うことはできますが、その消費方法については日本よりはるかに神経を使う必要があります。州によって多少温度差はあるかもしれませんが、基本的には飲むべき場所で飲むことが求められます。
これもまた上記と同じ頃、ある疲れた日、日本のコンビニの感覚で缶ビールを買って歩きながら飲もうとした私を、あの親切な酒屋のご主人が引き留めてくれなかったら、多少なりとも警察のご厄介になっていたかもしれません。上記同様、「となりは何をする人ぞ」の国では、酒は好き(恐らく日本人よりも)ではあるけれども、我々の想像以上に社会的脅威でもあるのだろうと実感した一幕でした。
かように、アメリカの移民社会の常識というのは我々のそれとは異なる部分が多く、特に事情に疎い初めての訪問者などには、理解不足が原因で大きなトラブルに発展する可能性もあります。これがビジネスの舞台ともなればなおさらで、相手の文化への理解が商談成功への大きなカギとなることでしょう。
つれづれなるままに書き綴ってみましたが、機会があれば続きも考えてみたいと思います。
中小企業診断士 中原健一郎