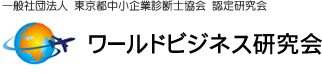<エピソード> いつものようにホーチミンのサービスアパートメントの前でタクシーを拾い、講義の為に大学に向かいました。歩けば、10分程度で行ける所だが、歩いている人は全くいません。ほとんどがバイクで、そこを遠慮がちに4輪車が走っています。バイクの音はけたたましいが、それほどスピードを出している訳ではありません。少しでも良い位置取りをしようと、隙あらば、とバイクの頭を突っ込んできます。そんな時だった、目の前のタクシーに中年の女性が乗ったバイクが接触し、転倒しました。タクシーの男性運転手は慌ててドアを開けて飛び出し、転倒した女性を起こそうとしましたが、女性は自分で起き上がりました。一瞬緊張したが、それを見てほっと安心しました。しかし、その時、想定外のことが起きました。いきなりその女性が、タクシーの運転手の顔面にパンチを繰り出したのです。そしてそのパンチが運悪く運転手の目に入ったらしく、その運転手はボンネットの上に突っ伏して暫く動けませんでした。その後は2人の激しい口論となりました。(2013年10月)

<個人主義と集団主義>
さて、このような時にどんな行動をとるかは、文化を反映するだろうか?交通事故でこのような行動をとることは日本ではあり得ないが、ましてや女性です。しかし、自己主張の激しいベトナムでは、さもありなん、と思いました。なぜ自己主張が激しいと感じたかは、学校で講義をし、質問を取った時の学生の態度です。ホフステードによれば「個人主義的社会の特徴として、生徒は授業中に個人として発言することが期待されている」(注1)とありますが、そのことに身をもって感じていたからです。
しかし、そこでホフステードのベトナムの個人主義指標スコア(注2)を見ると、ベトナムはスコア20となっており、日本のスコア46に比べても集団主義的な位置づけになっています。「文化の比較をするときは、民族集団、言語集団、宗教集団や国籍を用いることができるが、国籍を単位として比較することが最も現実的なやり方である。理由は手っ取り早いことと、データを集めやすいからである。ただし、その場合、充分な注意を要する」と言う主旨のことが記載されています。(注3)本件の事例はまさしくこの“但し書き”に該当する事例だと思います。

ベトナムの場合、南北に長い国であり、気候が違う事、南北に分断され、異なった政治環境下にあり、互いに戦ったという歴史を背負っていますが、ホフステードの個人主義指標スコアは首都であるハノイの文化を反映したものになっているのではないかと感じました。ベトナムは長らく中国の支配下で中国文化の影響を受けてきましたが、1882年にフランス軍がハノイを占領したことを契機として実質的にフランスに植民地化されました。その後第2次世界大戦初期の1940年にフランスがドイツに敗れると日本軍が進駐してきましたが、1945年8月のポツダム宣言で北部は中国、南部はイギリスの支援でフランスが再度支配することとなり、1975年4月30日のサイゴン陥落までフランス(途中1954年3月のディエンビエンフーの戦い後は実質的にアメリカ)の統治下にありました。このようなことから、南部にはフランス文化(個人主義スコア71)やアメリカ文化(同91)が根付いており、このような国ではその背景を考慮する必要があるのではないかと思います。ホフステードの76の国と地域のうち、ベトナム以外にも国籍で文化を判定するのは相応しくない国があるかもしれません。例えば宗教や言語で分断されている国があり、調査対象の都市が偏っていないかを確認する必要があります。
松村正之
注1:ホフステード「多文化世界」111P表4-4
注2:同84P
注3:同18P