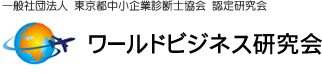当分科会も、食べ物の話になると盛り上がります。世界を渡り歩いてきた診断士の集まる会ゆえに、その所見も千差万別で大変興味深いのですが、食事についていえば「美味い」と同様にその逆の話が盛り上がることもあり、「アメリカはなぜ郷土料理的なものがあまりないのか」という素朴な疑問が持ち上がりました。
日本の約26倍もの国土を持つ国ですので、その分食事も地域によって多種多様という方が自然だと思うのですが、実際のところはそうではないらしく、国内どこでも食べられそうな“アメリカン”な食事にありつくというのが相場のようです。ニューヨークの郷土料理は?と聞かれて何かを思い浮かべられる人はほとんどいないでしょう。

あらゆる形態の飲食店が立ち並ぶが・・・
結局のところ、良くも悪くも調理に工夫を重ねてグルメを満喫しようなどという「気」がそもそも乏しいよね、というところで意見の一致を見たわけなのですが、このような風土がどのようにして生まれたのか、一部歴史的な事実も含めて私の見解を述べたいと思います。
私はこの根源を、厳格なプロテスタントの節制的、抑制的な行動理念、勤勉を旨とする労働観に見出すことができると考えています。
聖書の世界を遡ると、本来、労働はアダムが禁断の実を食べてしまったことに対する「罰」であり、当然避けられるべきものという考え方があったはずです。古代ギリシアやローマでは労働は奴隷に担わせていましたが、同じような感覚がキリスト教の隆盛後も聖書の考えと相まってヨーロッパには相当残っていたと考えるのが自然でしょう。
その後、中世を通じてカトリックが美食や享楽を推奨していたとは思いませんが、労働は少なくとも神への祈りの時間よりは下に置かれていたと考えてよいはずです。ところがそんな考え方に転換点をもたらしたのが16世紀の宗教改革で始まったプロテスタントでした。
とくに厳格な戒律や清貧で知られるカルヴァン派は、予定説(死後天国に行ける者と地獄に堕ちるものは予め神によって決められているという考え方)にもとづき、自らの職業にひたむきに従事することは、「その対価を得ることを含めて」神の御心にかなうものであるという主張を展開しました。
この考え方が多くの中小商工業者や労働者にとって受け入れやすかったことは、中小企業診断士に限らず納得できると思います。そして一生懸命働かずに美食・飽食やその他の安楽に身を委ねることは必然、神の御心にかないにくくなっていきます。
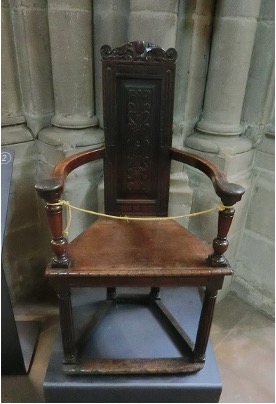
やがてヨーロッパ各地に広まったカルヴァン派はイギリスでは「ピューリタン(清教徒)」と呼ばれ、国教会との軋轢の中で信仰の自由を求めて、イングランドのプリマスから新大陸アメリカのプリマスへ渡った人たちがいました。これがピルグリム・ファーザーズ(巡礼始祖)です。
現代のアメリカ人が皆、節制的な生活を旨としているとは正直私も思いませんが、当時の巡礼始祖たちが、カルヴァン派の影響を色濃く保っていたことは想像に難くありません。
ここに、勤勉で禁欲的によく働きよく祈るというアメリカ人の精神的土台が築かれたのだと思います。この視点から言えば、アメリカという国は信仰のために(によって)作られたと言っても良いでしょう。
この頃のアメリカ人の姿に近い生活を窺い知ることは実は割と容易で、東部ペンシルベニア州を中心に「アーミッシュ」と呼ばれる移民当時の生活様式を頑なに守り通しているコミュニティーが今でもあります。
彼らは幌馬車に乗り、電気を使わず、清貧を旨とし自給自足の質素な食生活を送っています。この生活スタイルがアメリカの“原点”であり、この国の生活文化の基礎となって、フロンティアと共に西へ南へと広まったのだと私は考えています。
さてイギリスの清教徒たちはクロムウェルの有名なピューリタン革命によって一時期英国史の檜舞台に躍り出ますが、やはり国教会の勢力には及ばず衰退の道をたどることになります。しかし今日のイギリスの食卓が、グルメを旨とする人たちからすれば余り魅力的とは映らないのも、当時のピューリタニズムの影響と無縁ではないのだろうと思います。

一方のカトリック諸国では、美食や飽食に対する背徳感がプロテスタントに比べて醸成されにくかったという消極的な理由もあって、フランス料理やイタリア料理などの世界に名だたる料理が確立されていくことになります。 この違いはオランダとベルギーを比較するとより顕著で、ベルギーの北半分は同じオランダ語圏のオランダ系の人々が暮らすにもかかわらず、カトリックのベルギーとプロテスタントのオランダでは食事の質がまるで違います。オランダ南部の大都市ロッテルダムからベルギー北部の大都市アントワープ(フランダースの犬で有名)までは列車や車で1時間ほどですが、どうしても食事にこだわりたい夜は、移動時間分の価値は十分にあるかもしれません。

また、この違いは宗教的背景のみに起因するものではないことも確かで、世界を見渡せば食文化の発達要件には地域の緯度がかなり重要であることが分かります。緯度が高すぎても(寒すぎても)、低すぎても(暑すぎても)美食には具合が悪く、全体的に高緯度帯に位置するヨーロッパでは、“南”ヨーロッパこそ中緯度帯で、豊富な作物の恩恵に与れることは大きな要因でしょう。
ヨーロッパではこの地理的位置関係と宗教分布図が概ね重なって、食文化の大きな違いを生み出すことになったと言えるのではないでしょうか。

豊富な柑橘類と、ワインと
話をアメリカに戻しますが、現代のアメリカ事情から俯瞰した“米国料理”に対する考察もありました。一つは大規模農場による均一大量栽培・収穫であるため、山間小規模農業が主体の日本に比べれば地域差が生まれにくいこと。大海原のごとく地平線の彼方に続く小麦や大豆、とうもろこし畑の景色こそ、アメリカの原風景だと思います。

そしてもう一つに、移民国家であるがゆえに、どんな人々の口にも合う、普遍的な味が好まれるようになったのではないかという意見です。確かに、寿司や納豆は好きな人も多いですが、「無理」という人が日本人でも一定数います。いずれもアメリカで郷土料理が発達しにくい原因として、的を得た意見だと思います。
移民国家ゆえに世界各国の食文化がアメリカで花開くということにはならなかったのは、皮肉でもあり、アメリカ人の食に対する姿勢を示す一つの証左なのかもしれません。そんな中でどうやら市民権を得ているようなのがお隣りのメキシカンと中華ですが、いずれもかなり「ファストフード化」されてアメリカ社会に吸収されている印象があります。
地方都市の商業施設に入っているフードコートは言うに及ばず、サンフランシスコやニューヨークのチャイナタウンのレストランであっても、ローカライズされた店ほど、本場広州や北京の味とは似て非なるものになってくるようです。これがもしかしたら、移民国家で通用する、人類の最大公約数的な味覚に近いのかもしれません。

この味は受け付けないという地球人もまずいないと思われる
色々述べましたが、私は一般に食事が美味しくないと言われている国の人たちが“バカ舌”であるなどとは露ほども思っておらず、その地域の食文化に決定的な影響を及ぼした地理歴史、文化的背景が主因として必ず潜んでいるのだと思います。その地を訪れて食べ物に触れ、昔年から今のその食生活に繋がった道のりを紐解いていくことは、まるでタイムマシンに乗って過去から現代に戻ってくるような思考実験的楽しみがあります。
アメリカで食事を堪能するということは、舌鼓を打つことよりも、マクドナルドやタコベルも含めてあるがままのアメリカンフードにどっぷり浸って、その境地に至るまでの開拓者たちのフロンティア・スピリットに思いを馳せることなのかもしれません。
中小企業診断士 中原健一郎